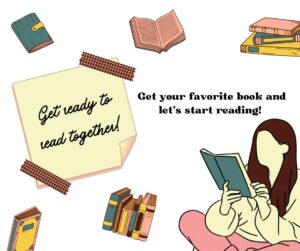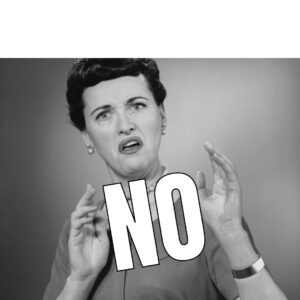あわせて読みたい
防衛機制(Defense Mechanism)の4分類
防衛機制とは、私たちが不安やストレスに対処するために無意識に使用する心理的なメカニズムです。これらのメカニズムは、私たちの心の安定を保つために重要な役割を果たします。防衛機制は、一般的につのカテゴリーに分類されます。
あわせて読みたい
エゴ(自我、ego)とは
エゴ(自我)は、心理学において非常に重要な概念であり、特に精神分析学の創始者であるジークムント・フロイトによって広く知られるようになりました。エゴは、個人の意識的な自己認識や自己評価、自己制御に関連する心理的な構造を指します。
目次
防衛機制とは
防衛機制(Defense Mechanism)は、精神分析における概念であり、ジークムント・フロイトによって提唱されました。
防衛機制は、自我が外部からのストレスや内的な葛藤から自分を守るために無意識的に行う心理的なプロセスです。これにより、個人は精神的な安定を保つことができます。
防衛機制の種類
防衛機制にはさまざまな種類があり、それぞれ異なる方法で自我を守ります。以下に主要な防衛機制をいくつか紹介します。
1. 抑圧(Repression)
抑圧は、受け入れがたい思考や感情を無意識の中に押し込めることです。
これにより、個人はその思考や感情を意識的に認識することなく生活することができます。
あわせて読みたい
抑圧(Repression)とは
抑圧(よくあつ)は、精神分析の創始者であるジークムント・フロイトによって提唱された防衛機制の一つです。
抑圧は、個人が受け入れがたい、または不快な思考、感情、欲望、記憶などを無意識に押し込め、意識から締め出すプロセスです。
これにより、個人はこれらの不快な要素を意識的に認識することなく生活を続けることができます。
2. 抑制(suppression)
抑制(よくせい)は、意識的に不安や不快を感じるような出来事や考えを避けるプロセスです。抑圧と似ていますが、抑制は意識的に行われる点が異なります。
あわせて読みたい
抑制(suppression)とは
抑制(よくせい)は、防衛機制の一つであり、意識的に不安や不快を感じるような出来事や考えを避けるプロセスです。
抑圧と似ていますが、抑制は意識的に行われる点が異なります。
3. 否認(Denial)
否認は、現実の出来事や感情を認めず、存在しないものとして扱うことです。
これは、特にショックやトラウマを経験した際に見られることが多いです。
あわせて読みたい
否認(Denial)とは
否認は、現実の出来事や感情を認めず、無視することで心理的な安定を保つ防衛機制です。
これは、受け入れがたい現実や感情に直面した際に、それを認識しないことで不安やストレスを回避しようとする無意識のプロセスです。
あわせて読みたい
「否認」(悲嘆のモデル)
アルフォンス・デーケンの悲嘆の12段階モデルのうちの2段階目「否認」についてまとめています。
あわせて読みたい
悲嘆(グリーフ、grief)のモデル
人生の中で衝撃的な別れを体験すると、人は「悲嘆(グリーフ)」の状態に陥ることがあります。それに伴い場合によっては精神的・身体的苦痛を味わうことがあります。
4. 投影(Projection)
投影は、自分の中にある受け入れがたい感情や思考を他人に押し付けることです。
例えば、自分が他人に対して感じている敵意を、他人が自分に対して敵意を持っていると感じることです。
あわせて読みたい
投影とは(Projection)とは
投影(Projection)は、精神分析における防衛機制の一つであり、自分の受け入れがたい感情や思考を他人に押し付けることを指します。
これは無意識的に行われるものであり、自分の内面の否定的な側面を他人に投影することで、自分を守ろうとする心理的なメカニズムです。
5. 置き換え(Displacement)
置き換えは、ある対象に向けられた感情や衝動を、より安全な別の対象に向けることです。
例えば、上司に対する怒りを家族に向けることです。
あわせて読みたい
置き換え(Displacement)とは
置き換え(Displacement)は、感情や態度などを本来の対象ではなく、別の対象に向けて表現、発散する防衛機制です。
これは、元来の対象に対して感情を表現することが危険で不安を感じる場合に、より安全だと思われる別の対象に向けて感情を表出することを意味します。
6. 昇華(Sublimation)
昇華は、社会的に受け入れられない衝動や欲求を、社会的に受け入れられる形に変換することです。
例えば、攻撃的な衝動をスポーツや芸術、学び、ボランティア活動などに向けることです。
あわせて読みたい
昇華(Sublimation)とは
昇華(Sublimation)は、フロイトによって提唱された防衛機制の一つで、社会的に受け入れられない欲求や衝動を、社会的に受け入れられる形に変換するプロセスです。
これは、無意識のうちに行われることが多く、個人が内的な葛藤や不安を解消するための手段として機能します。
7. 反動形成(Reaction Formation)
反動形成は、受け入れがたい思考や感情を、その反対の行動や態度で表現することです。
例えば、嫌いな人に対して過剰に親切にすることです。
あわせて読みたい
反動形成(Reaction Formation)とは
反動形成は、個人が受け入れがたい感情や衝動を抑圧するために、その感情や衝動とは正反対の行動や態度を取ることです。
例えば、強い憎しみを抱く相手に対して、好意的に愛想よく振る舞うことが挙げられます。
これは、無意識の中で抑圧された感情が意識に上がるのを防ぐためのメカニズムです。
8. 知性化(Intellectualization)
知性化は、感情的な問題を理論的・抽象的に考えることで、感情から距離を置くことです。
これにより、感情的な痛みを軽減することができます。
あわせて読みたい
知性化(Intellectualization)とは
知性化は、防衛機制の一つで、感情や衝動を理性的に分析し、知的な理解を通じてそれらを処理しようとする方法です。
これにより、感情的な苦痛を軽減し、冷静に対処することができます。
9. 合理化(Rationalization)
合理化は、自分の行動や感情を論理的に正当化することです。
これにより、自己評価を保つことができます。
あわせて読みたい
合理化(Rationalization)とは
合理化とは、防衛機制の一つで、個人が自分の行動や感情を正当化するために、論理的で受け入れやすい理由を見つけ出すことです。
これにより、自己評価を保ち、罪悪感や不安を軽減することができます。
10. 退行(Regression)
退行は、ストレスや不安に対処するために、より幼い行動や態度に戻ることです。
例えば、大人がストレスを感じたときに子供のように振る舞うことです。
あわせて読みたい
退行(Regression)とは
退行(regression)は、個人がストレスや不安に直面したときに、より幼い段階の行動や思考パターンに戻ることを指します。
これは、心理的な防衛機制の一つであり、無意識のうちに行われることが多いです。
退行は、個人が現在の状況に対処するための一時的な手段として機能します。
11. 同一視(Identification)
同一視は、他人の特性や行動を自分のものとして取り入れることです。
これにより、自己評価を高めたり、安心感を得ることができます。
あわせて読みたい
同一視(Identification)とは
同一視(identification)は、個人が他者の特性、行動、信念を自分自身のものとして取り入れる心理的なプロセスを指します。
これは、無意識のうちに行われることが多く、自己のアイデンティティを形成する上で重要な役割を果たします。
同一視は、特に子供が親や教師、友人などの重要な他者と同一視することで、社会的な規範や価値観を学ぶ過程でよく見られます。
12. 打ち消し(Undoing):
過去の行動や思考を取り消すために、反対の行動を取ることです。
例えば、誰かを傷つけた後、その人に対して過剰に親切にしたりすることです。
あわせて読みたい
打ち消し(Undoing)とは
打ち消し(Undoing)は、防衛機制の一つで、過去の行動や思考を取り消したり、無効にしたりすることで、不安や罪悪感を軽減しようとする心の働きです。打ち消しは、特に罪悪感や後悔を感じる状況で見られることが多く、過去の行動を修正しようとする試みとして現れます。
13. 分裂(Splitting)
物事や人々を「全て良い」または「全て悪い」と極端に二分することで、不安やストレスから自分を守る心の働きです。
あわせて読みたい
分裂(Splitting)とは
分裂(Splitting)は、防衛機制の一つで、特に幼少期や精神的に不安定な時期に見られることが多いです。分裂は、物事や人々を「全て良い」または「全て悪い」と極端に二分することで、不安やストレスから自分を守る心の働きです。
14. 理想化(Idealization)
他者や自己を過度に理想化し、現実の欠点や弱点を無視することで、不安やストレスを軽減しようとする心の働きです。
特に人間関係や自己評価において顕著に見られます。
あわせて読みたい
理想化(Idealization)とは
理想化(Idealization)は、防衛機制の一つで、他者や自己を過度に理想化し、現実の欠点や弱点を無視することで、不安やストレスを軽減しようとする心の働きです。
理想化は、特に人間関係や自己評価において顕著に見られます。
15. 脱価値化、切り下げ(devaluation)
他者や自分自身の価値を過小評価し、否定的に捉える心理的なプロセスを指します。
これは、特に境界性人格障害(BPD)や自己愛性人格障害(NPD)などの人格障害に関連して見られることが多いです。
脱価値化は、理想化(idealization)と対をなす概念であり、これらのプロセスが交互に現れることがあります。
あわせて読みたい
脱価値化、切り下げ(devaluation)とは
脱価値化(切り下げ)とは、他者や自分自身の価値を過小評価し、否定的に捉え、心理的な安定を保つ防衛機制です。
特に自己評価が低下している場合や、他者との関係において不安や怒りを感じている場合によく見られます。
あわせて読みたい
理想化(Idealization)とは
理想化(Idealization)は、防衛機制の一つで、他者や自己を過度に理想化し、現実の欠点や弱点を無視することで、不安やストレスを軽減しようとする心の働きです。
理想化は、特に人間関係や自己評価において顕著に見られます。
防衛機制の役割と影響
防衛機制は、短期的には個人を守る役割を果たしますが、長期的には問題を引き起こすことがあります。
例えば、抑圧された感情や思考は、無意識の中で蓄積され、後に精神的な問題を引き起こす可能性があります。
また、防衛機制が過度に使用されると、現実との適応が難しくなることがあります。
防衛機制の発展と研究
防衛機制の概念は、ジークムント・フロイトによって提唱され、その後、娘のアンナ・フロイトによってさらに発展されました。
アンナ・フロイトは、防衛機制を体系化し、さまざまな種類の防衛機制を明確にしました。
また、ジョージ・E・ヴァイラントは、防衛機制を成熟度に基づいて分類し、精神病的防衛、未熟な防衛、神経症的防衛、成熟した防衛の4つのレベルに分けました。
防衛機制の応用
防衛機制の概念は、心理療法やカウンセリングの現場で広く応用されています。
セラピストは、クライアントがどのような防衛機制を使用しているかを理解し、それに基づいて適切な支援を提供します。
また、防衛機制の理解は、自己理解を深め、より健康的な対処方法を見つける手助けとなります。
まとめ
防衛機制は、自我が外部からのストレスや内的な葛藤から自分を守るために無意識的に行う心理的なプロセスです。
さまざまな種類の防衛機制があり、それぞれ異なる方法で自我を守ります。
防衛機制は短期的には個人を守る役割を果たしますが、長期的には問題を引き起こすことがあります。
防衛機制の理解は、自己理解を深め、より健康的な対処方法を見つける手助けとなります。
あわせて読みたい
防衛機制(Defense Mechanism)の4分類
防衛機制とは、私たちが不安やストレスに対処するために無意識に使用する心理的なメカニズムです。これらのメカニズムは、私たちの心の安定を保つために重要な役割を果たします。防衛機制は、一般的につのカテゴリーに分類されます。
あわせて読みたい
エゴ(自我、ego)とは
エゴ(自我)は、心理学において非常に重要な概念であり、特に精神分析学の創始者であるジークムント・フロイトによって広く知られるようになりました。エゴは、個人の意識的な自己認識や自己評価、自己制御に関連する心理的な構造を指します。