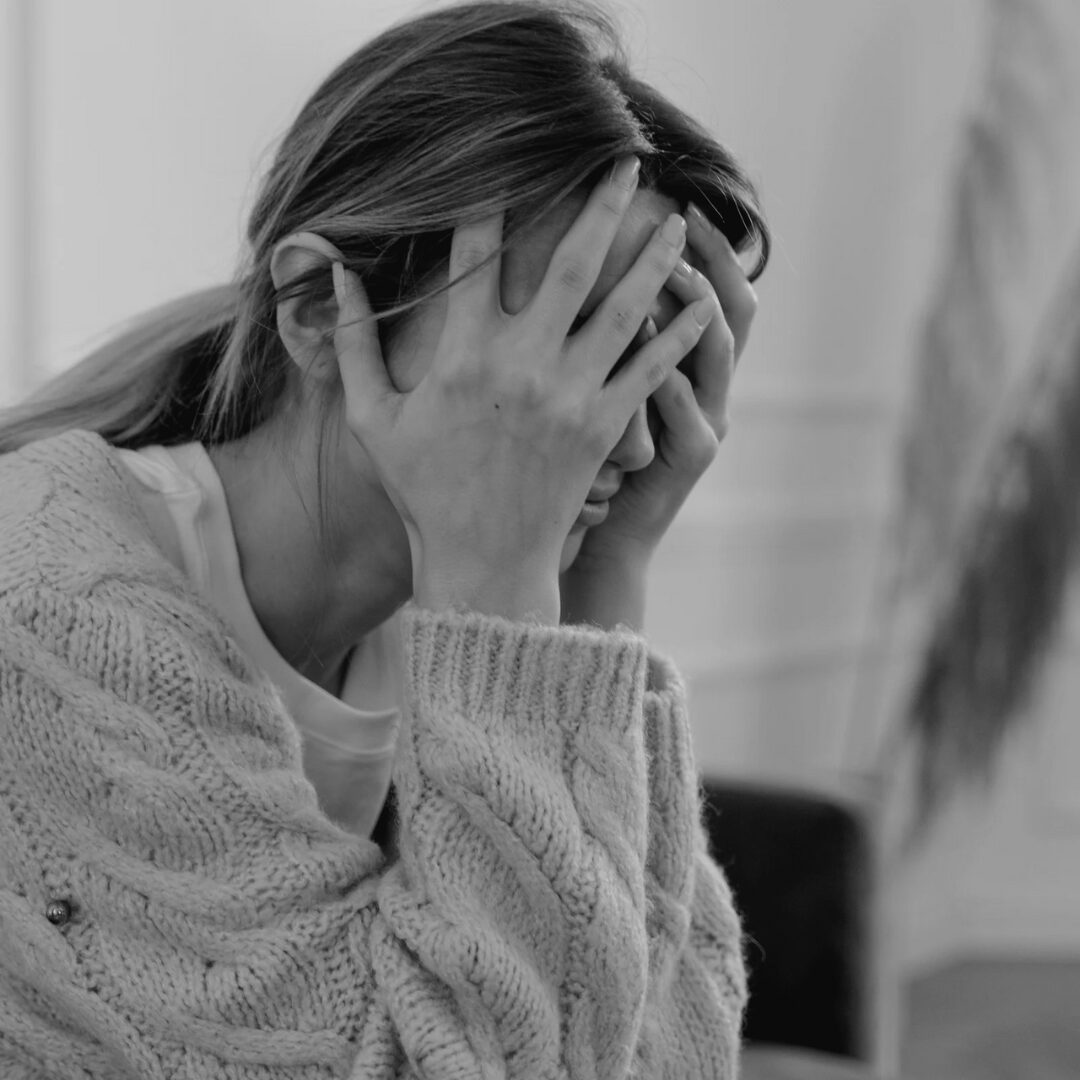グリーフ(悲嘆、grief)とは
皆さまは「悲嘆」「グリーフ」という言葉を聞いたことがありますでしょうか?
日本終末期ケア協会では、グリーフのことを以下のように定義されています。
グリーフ(grief、悲嘆)…近親者との死別・離別をはじめとして、さまざまな愛情や依存の対象を喪失した際に生じる反応のこと。
悲嘆は、単に嘆き悲しみ、気分が落ち込むといった心の反応だけではありません。
睡眠障害、疲労感、食欲の低下などによる身体的な反応、日常生活や行動的な変化、スピリチュアルな変化を伴う反応も含まれます。
この反応は、愛する人との死別の際に起こるだけではなく、人間関係に終止符を打ったり人生の大きな変化があったときにも同様のプロセスを経験することが分かっています。
死別や生別・別離(家族・親族、配偶者、パートナー、子ども、ペット、友人など)
災害、事故、病気・死の宣告(自分や身近な人、大事な人も含む)キャリア(失職、転職、転勤など)、引っ越し、留学、家や所有物の紛失 など
非常に感情が揺れ動く体験をするため、十分にケアがなされないとやがて精神的・身体的症状が現れる場合があります。(ペットロス症候群など)
立ち直るまでの期間には個人差があり、必ずしもこのプロセス通り順番に進むとは限りませんし、全てのプロセスを体験するとも限りません。
また、専門家に頼ってグリーフケアを行う場合もあれば、ある程度であれば個人で行うことも可能です。
ですが無理をしてご自身だけで癒そうとすると症状が悪化してしまう場合も考えられますので、遠慮なく専門家を頼ることも大切です。
(初めての心理カウンセリングを受ける場合は公認心理師、臨床心理士のカウンセリングがおすすめです)
あらかじめどんなプロセスを辿るのかを知っておくと、悲しみをゼロにすることはできないものの(ゼロにしようとすると逆に症状が悪化する場合があります)ひどい状況に陥りにくくなることがわかっています。
そして悲嘆から立ち直るプロセスの途中で、宗教やスピリチュアルの教えを学ぶ方もいます。
どこまで詳しく学ぶかは個人差があります。またスピリチュアル業界で言われているソウルメイト、ツインレイプログラム(サイレント期間・自己統合)などもおそらく悲嘆のモデルである程度説明がつくのかと思われます。
心理学の専門家の間では、悲嘆についての様々なモデルについて説明されています。
この記事では代表的なものをご紹介していきます。
 しな
しな私はコロナ禍のときにこのプロセスを体験しました。
離職、住み慣れた東京から地元への引っ越し、東京での親しい人達とのお別れ、祖父の死などが同時期に起こり非常に混乱しました。
現在は立ち直っていますが、引っ越し直後は何もできませんでした。
その後、心理学を学び、当時の私の身に何が起こっていたのかを知ることができました。(もっと早く知っておきたかったです…笑)






アルフォンス・デーケンの悲嘆の12段階モデル
アルフォンス・デーケンの悲嘆の12段階モデルは、死別や重大な喪失に直面した人々が経験する感情的なプロセスを詳細に説明しています。
死別や生別・別離(家族・親族、配偶者、パートナー、子ども、ペット、友人など)
災害、事故、病気・死の宣告(自分や身近な人、大事な人も含む)キャリア(失職、転職、転勤など)、引っ越し、留学、家や所有物の紛失
このモデルは、以下の12の段階から成り立っています。
立ち直るまでの期間には個人差があり、必ずしもこのプロセス通り順番に進むとは限りませんし、全てのプロセスを体験するとも限りません。
また、専門家に頼ってグリーフケアを行う場合もあれば、ある程度であれば個人で行うことも可能です。
ですが無理をしてご自身だけで癒そうとすると症状が悪化してしまう場合も考えられますので、遠慮なく専門家を頼ることも大切です。
(初めて心理カウンセリングを受けられる場合は、公認心理師・臨床心理士のカウンセリングがおすすめです)
1. 精神的打撃と麻痺状態
愛する人の死(またはそれに準ずる重大な喪失)という衝撃によって、一時的に現実感覚が麻痺状態になります。
頭が真空になったようで、思考力が落ち込むことがあります。
2. 否認
死または喪失したという事実を認めることを否定します。
「あの人が死ぬはずがない。(私の側からいなくなるはずがない。)きっと何かの間違いだ」
ペットロスの場合ですと
「ペットの○○が亡くなってしまった/いなくなってしまったはずがない。」
という心理です。
3. パニック
身近な人の死または重大な喪失に直面した恐怖から、極度のパニック状態に陥ります。
これは悲嘆のプロセスの初期に顕著な現象です。
4. 怒りと不当感
ショックがやや収まってくると、「なぜ私だけが、こんな目に合わなければならないのか」という不当感が沸き上がります。
一時的に怒りや不当感を感じることは仕方のないことですし、きちんと自分で受けとめて昇華する必要があります。
東洋医学では怒りを抱えたままでいると、肝臓に負担がかかることがあると言われております。
自分自身の身体を守るためにも、ある程度怒りや不当感を感じきったらその感情を受け入れていく必要があります。


5. 敵意とうらみ(ルサンチマン)
周囲の人々や故人に対して、敵意という形でやり場のない感情をぶつけます。
特に医療関係者やカウンセラーなどに向けられることが多いです。
また身近な人(家族、配偶者、パートナー、友人など)に気持ちをぶつけてしまう方もいます。
ある程度は仕方のないことですが、なるべく早くこの段階を抜け出せることが望ましいです。
あまりにも長くこの段階を続けてしまうと、身近にいる本当に大事な人達との関係性を自ら破壊してしまうことに繋がってしまいます。
また、ぶつけられてしまった方はあまり気にしすぎないことも重要です。
気持ちをぶつけてしまっている人はいつもの状態、本来のその人の状態ではないことを理解し、時間が経てばまたその人が本来の状態を取り戻す…ということを信じてあげることも大切です。
感情をぶつけられてしんどい場合は、少しその方との距離をとりましょう。




6. 罪意識
「こんなことになるのなら、生きているうちに、もっとこうしてあげればよかった」という心境で、自分を責めることになります。
大事な人やペットが身の回りからいなくなる前に、後悔しないよう接していくことが大切ですね。
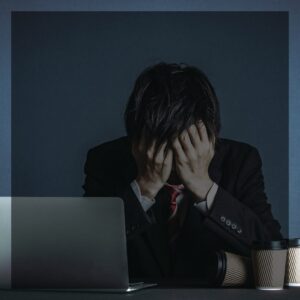
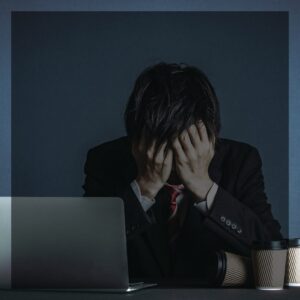
7. 空想形成・幻想
故人がまだ生きているかのように思い込み、実生活でもそのように振る舞います。例えば、故人の部屋をそのままにしておくことがあります。
8. 孤独感と抑うつ
葬儀などが一段落し、周囲が落ち着いてくると、紛らわしようのない寂しさが襲ってきます。
9. 精神的混乱とアパシー(無関心)
日々の生活目標を見失った空虚さから、どうしていいかわからなくなり、あらゆることに関心を失います。
10. あきらめー受容
自分の置かれた状況を「あきらか」に見つめて受け入れ、つらい現実に勇気をもって直面しようとする努力が始まります。
11. 新しい希望ーユーモアと笑いの再発見
こわばっていた顔にも少しずつ微笑みが戻り、ユーモアのセンスもよみがえってきます。


12. 立ち直りの段階ー新しいアイデンティティの誕生
立ち直りの段階を迎えます。
愛する人を失う以前の自分に戻るのではなく、新たなアイデンティティを獲得し、より成熟した人格者として生まれ変わることができます。


まとめ
グリーフ(悲嘆)を体験すると精神的・身体的負担が数ヶ月〜数年単位で続く場合があります。
ケアには自分で行うか、専門家や身近な人に頼るかなどの方法がありますが、なるべく重症化しないようにしたいものですね。



一人で苦しむのではなくできるだけ早めに専門家に頼りましょう。
公認心理師・臨床心理士に相談してみましょう。